第10回ウェルビーイングラウンジ“Controlling HIV: Clinical and Public Health Perspectives” 「H I Vをコントロールするには:臨床と公衆衛生の視点から」
- TOP
- ー
- イベント・セミナー開催情報
- ー
- 第10回ウェルビーイングラウンジ“Controlling HIV: Clinical and Public Health Perspectives” 「H I Vをコントロールするには:臨床と公衆衛生の視点から」

:東京科学大学 湯島キャンパス M&Dタワー8階 Glab
2025年4月18日(水) 17:00
2025年4月18日に、 感染症、国際保健分野で世界トップレベルの研究を続けるジョンズ・ホプキンス大学よりラリー・チャン教授、ケイトリン・ケネディ教授をお招きし、第10回ウェルビーイングラウンジを開催しました。このラウンジは、東京科学大学の感染症対策を進める感染症センター(TCIDEA)との共催で行われました。現地・オンライン併せて120名以上の方にご参加いただき、活発な議論が繰り広げられました。
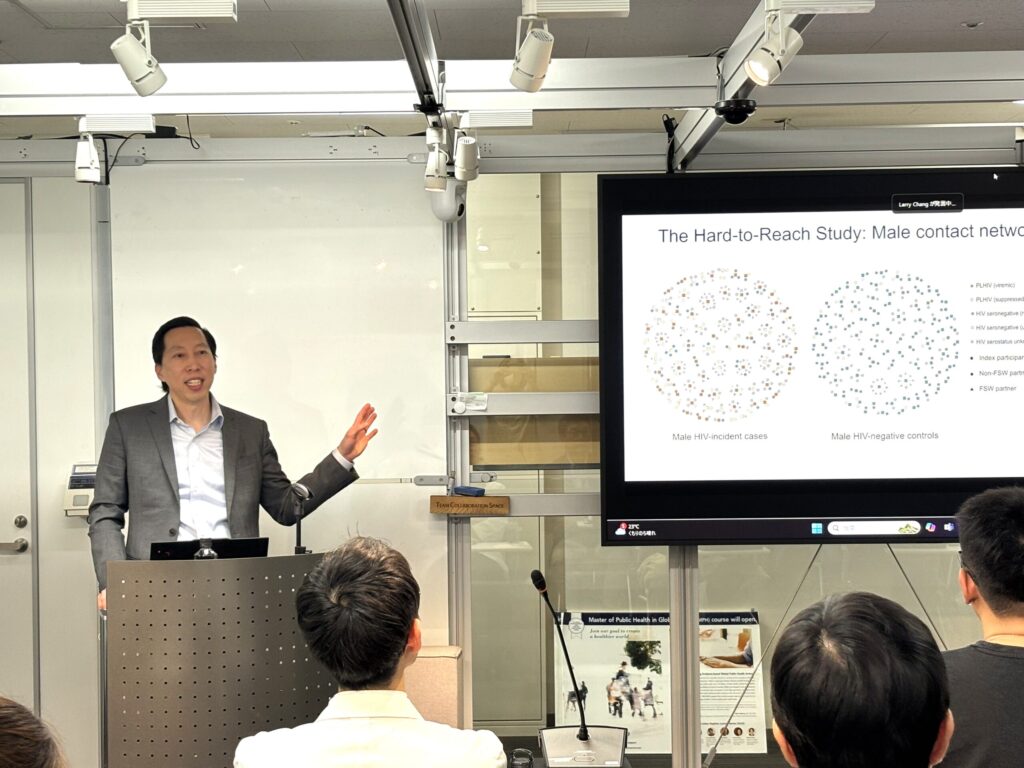
まず、ラリー・チャン教授からは、ウガンダ南部のルウェロ地域で進められている Rakai Health Sciences Program(RHSP) と、その地域で実施されている40年以上続く疫学コホート研究Rakai Community Cohort Study(RCCS) の最新成果が紹介されました。
まず、HIV流行の変化として、ウイルスの再集合や多様化が進み、特にウガンダでは時間の経過とともに遺伝的多様性が大きく拡大していることが示されました。これは治療効果だけでなくワクチン開発にも重要な示唆を与えるものだと言えます。また、サブタイプによってHIV進行速度が異なることも明らかになっているそうです。
社会行動学的研究では、HIV有病率が30~40%と極めて高い湖岸の漁村コミュニティの特徴が紹介されました。漁民が長期間湖上で生活すること、移動が多いこと、そして薬の「シェア」が広く行われていることが、薬剤耐性パターンを生み出す一因となっているとの説明が印象的でした。定性的調査で確認された薬の融通行為はコホートデータでも確認され、薬を「分け与える」人ほどウイルス抑制が不十分であることも明らかとなっているそうです。

さらに、RakaiではHIV以外の新興感染症研究も行われています。クリミア・コンゴ出血熱(CCHF)についてはヤギの80%が感染歴を持ち、人間でも相当数の陽性が見られたとのことでした。また、都市化と非感染性疾患(NCD)とHIVの「シンデミック」を扱う研究では、心機能検査、肺機能検査、空気質センサーによる曝露測定など多面的なデータ収集が行われていることも紹介されました。
質疑応答では、COVID-19の影響や、長期作用型注射製剤(long-acting injection, LAI)を用いたHIV制御の可能性、資金削減による今後の懸念が議論されました。移動の多い人々に対し長期作用型治療を継続することは容易ではなく、さらに国際的な資金削減によりウガンダでは専用HIVクリニック閉鎖の動きも出ており、今後のサービス維持が大きな課題となっているそうです。

また、講演終了後も、TCIDEAの感染症専門医によるより専門的な質疑も繰り広げられ、HIVに関する国際保健の最前線を理解するための有意義なラウンジとなりました。

